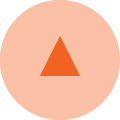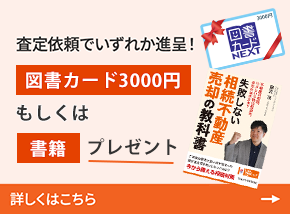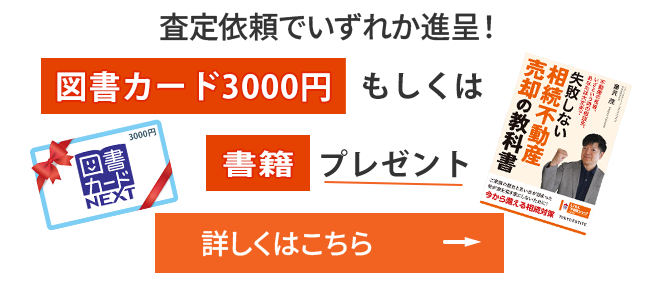Trouble
借地権・底地・訳あり
物件を売却したい方へ
- ホーム
- 借地権・底地・訳あり物件を売却したい方へ
目次
借地権・底地・訳あり不動産でも大丈夫。
スムーズに売却するために
「借地だから売れないかも」「再建築不可といわれた」「他社に断られた」──そんな訳あり不動産も、売却をあきらめる必要はありません。
借地権・底地・再建築不可・狭小地・事故物件など、一般的な不動産会社では対応が難しい物件でも、当ショップでは数多くの相談・売却実績があります。
このページでは、それぞれの物件の特徴や売却時の注意点、成功のポイントまで詳しくご紹介いたします。
LIXIL不動産ショップ TOKYO ESTATEでは、東京都北区を中心に、豊島区・板橋区・練馬区・文京区エリアで対応しております。
訳あり物件こそ、私たちの出番です。売却成功へ導く4つの強み
借地権・底地の専門知識と売却実績が豊富

一般的な不動産会社では対応が難しいとされる借地権・底地の売却も、法律・慣習・権利関係に精通したスタッフが在籍しているため、スムーズな売却を実現します。士業との連携や地主・借地人間の調整もお任せください。
再建築不可・狭小地・不整形地にも対応可能

建築基準法上の制限で再建築できない土地や、間口が狭く活用が難しい狭小地・不整形地なども、再利用プランや収益化の可能性をふまえた買取・仲介をご提案できます。他社で断られたケースにも対応実績あり。
事故物件の売却にも対応。心理的瑕疵の取扱い経験多数

自殺・孤独死・事件などによるいわゆる「事故物件」も、告知義務を踏まえたうえでの対応方法や販売戦略を熟知しています。心理的なハードルを下げる伝え方・価格調整・買取提案も可能です。
ワンストップ対応だから、安心して任せられる

複雑な権利関係の調整から、残置物の処分、近隣対応、契約・登記まで、すべて当ショップが窓口となって対応いたします。「どこに頼んでいいか分からない」という段階でもご安心ください。
借地・底地・再建築不可など、「売れないかもしれない」と感じていた不動産でも、経験と知識のあるプロに任せれば、きちんと売却できる道があります。まずは安心して、ご相談ください。
「借地でも売れる?」にお応えします。
借地権のしくみと売却のポイント
借地権とは?

借地権とは、他人が所有する土地を借りて建物を建てる権利のことを指します。
たとえば、「土地は地主のもの」「建物は自分のもの」という状態で長年住んでいるケースが該当します。
代表的な借地権には以下の2つがあります。
- 旧法借地権:借地借家法(旧法)に基づき、更新を重ねながら長期間使われてきた権利。借主の保護が強く、地主の承諾なしでは解除しづらい特徴があります。
- 定期借地権:契約期間(例:30年、50年など)があらかじめ決まっており、原則として更新ができないもの。更新の必要がない代わりに、契約終了時には土地を明け渡す必要があります。
借地権付き建物を相続した方や、空き家の状態で放置している方の中には、
「土地が自分のものではないから売れないのでは?」と不安を抱えるケースが多く見受けられます。
しかし、借地権自体にも市場価値があり、売却や買取が可能です。
借地権を売却する時の流れと注意点
売却の一般的な流れ
- STEP 1権利関係・契約内容の確認
-
借地契約書や更新履歴、名義状況を確認し、どのタイプの借地権かを明確にします。
- STEP 2地主への売却承諾交渉
- 多くの場合、借地権を第三者に売却するには地主の承諾が必要です。承諾料(名義書換料)を支払うケースもあります。
- STEP 3査定・販売活動
- 借地権付きの不動産として、買取または仲介で売却活動を進めます。買主が見つかりにくい場合は、買取の選択肢もご提案可能です。
- STEP 4契約・引き渡し・手続きサポート
- 売却にあたっては、土地の借地権関係書類や登記簿の調整が必要となることもあります。当ショップでは、士業と連携して一括対応いたします。
借地権売却の注意点
- 地主との関係性が鍵
地主が承諾に応じない場合、売却活動に支障が出ることがあります。当ショップでは、地主との交渉や調整を丁寧にサポートします。 - 契約書・更新記録が見つからない場合は早めに相談を
権利内容が不明確なままだと、売却が進みにくくなる場合があります。古い契約でも、内容整理と法的確認を行いながらご対応可能です。 - 借地人間のトラブルがある場合も調停人資格者が対応
相続で共有しているケースなど、意思決定が難しい場合もご相談ください。調停人資格を持つ担当者が中立的な立場で解決をお手伝いします。
借地権付きの不動産は、「土地が自分のものではない」という点から、売却が難しい・ややこしいと思われがちですが、正しい知識と交渉の工夫次第で、十分に売却可能です。
- 借地契約の種類や内容の確認
- 地主との関係性や承諾の取得
- 売却か買取か、最適な方針の見極め
これらを踏まえ、適切に進めていくことが重要です。

当ショップでは、「法務大臣認定裁判外紛争解決機関 日本不動産仲裁機構登録調停人」資格を持つ担当者が在籍し、借地トラブルや地主との交渉まで、安心してお任せいただけます。
「このまま相続していいのか迷っている」「売れるかどうか聞いてみたい」──そんな段階からでも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
底地は売れないと思っていませんか?
地主様向け・底地売却の進め方
底地とは?

底地(そこち)とは、「他人に貸している土地(借地)」の所有権のことを指します。
つまり、土地は自分のものですが、その上に他人が家を建てて住んでいるという状態です。
地主と借地人との間には借地契約があり、地主は「底地権者」として地代を受け取り続ける立場にあります。
底地をお持ちの方が抱えるお悩みには、以下のようなものがあります。
- 地代が安く、毎年の固定資産税のほうが高い
- 借地人との関係性が希薄・揉めている
- 相続で底地を受け継いだが活用方法がわからない
- 更地にしたくても建物が自分のものではないので動けない
一見ややこしそうな底地ですが、売却や買い取りも可能です。
借地人や不動産会社への売却、あるいは借地権との“等価交換”など、活用法は多様です。
底地を売却する時の流れと注意点
売却の一般的な流れ
- STEP 1契約状況・借地人との関係性の確認
- 契約書の有無、地代の支払い状況、更新履歴などを確認します。
- STEP 2売却方針の選定(誰に売るか)
- 借地人への売却、第三者への売却、不動産会社による買取など、方針を明確にします。
借地人に売る場合は、借地権と底地を一体化できるため、価値が高まりやすい傾向があります。
- STEP 3借地人への通知・協議
- 借地人がいる場合、売却の意思を伝え、内容に応じて調整や承諾が必要になります。
- STEP 4査定・売却活動・契約
- 底地の内容(地代・権利関係・エリア)に応じた適正な価格を算出し、売却へ進みます。
底地売却の注意点
- 借地人の合意が得にくいケースもある
借地人が売却や一括購入に消極的な場合、交渉や条件調整が必要になります。当ショップでは、中立的立場での調整役として対応可能です。 - 収益性と市場性のバランス
底地は地代収入が少額である一方、権利関係が複雑なため、市場性に限りがあるケースもあります。
当ショップでは、借地人への売却、第三者への提案、買取価格提示など柔軟な戦略をご提案できます。 - 相続や名義未変更の状態でも対応可能
名義が親のまま、権利関係が整理されていないといったケースでも、司法書士と連携して問題解決をサポートします。
底地のような「どう動いていいか分からない不動産」こそ、専門知識と経験が必要です。
当ショップでは、地主様・借地人の両者にとって納得のいく着地ができるように、調整から売却まで丁寧に対応いたします。
まずは現在の状況をお聞かせください。無料相談・無料査定にてご案内いたします。
「再建築不可」でも売却できます。
押さえておきたい基礎知識と進め方
再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、現行の建築基準法に適合していないため、新しく建物を建て直すことができない土地・建物のことを指します。
多くは、建築基準法上の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接しているなど)を満たしていないために、「再建築できない」と判断されています。
たとえば…
- 路地奥にある旗竿地
- 幅が狭い通路の奥まった敷地
- セットバック未対応の接道など
こうした物件は住宅ローンが付きにくく、一般には売りづらいとされますが、活用方法や買取ニーズが明確であれば売却は十分可能です。
再建築不可物件を売却する時の流れと注意点
- STEP 1法令・現況の確認
- 接道条件や登記簿の確認を行い、「なぜ再建築不可なのか」を明確にします。
- STEP 2査定・売却戦略の立案
- 活用できる方法(リフォーム・賃貸・資材置場・倉庫など)や、買取による再販・収益化を前提に査定します。
- STEP 3売却活動 or 買取提案
- 再建築不可物件に理解のある投資家・業者向けに販売を行うか、当ショップが直接買取も可能です。
注意したいポイント
- 相場価格よりも売却価格が下がる傾向にあります
建替えができない分、用途が限定されるため、価格は建築可能な物件より低めになります。 - 住宅ローンが付きにくいことを想定した販売戦略が必要
買主が現金購入を前提とするケースも多いため、専門的な販売戦略が不可欠です。
再建築不可物件も、売却先を見極め、最適な活用方法を描ければ、確実に出口があります。
当ショップでは、こうした物件の取り扱いに慣れた担当者が、査定・調査・買取まで一括対応。
「これ、本当に売れるのかな?」と不安な物件こそ、まずはお気軽にご相談ください。
狭小地・不整形地も売却できます。
“使いにくい土地”の活用と売却の考え方
狭小地・不整形地とは?

狭小地とは、一般的に15坪(約50㎡)以下の小さな土地のことを指し、不整形地とは、台形・L字型・三角形など整っていない形状の土地を指します。
どちらも「使いにくい」「建築しづらい」とされるため、一般的な売却市場では敬遠されがちです。
ですが、立地や用途によっては「小回りの利く収益物件」「事業用地」「駐車場」などとしてニーズがあるケースも多く、的確なターゲットに訴求できれば売却成功の可能性は十分にあります。
狭小地・不整形地を売却する時の流れと注意点
- STEP 1現地調査と建築制限の確認
- 実際の土地の広さや形状、接道の有無、用途地域などの法的条件を確認します。
- STEP 2最適な活用法・売却方針の検討
- 狭小住宅向け建築用地、資材置場、店舗用地、駐車場など、立地と形に応じた使い道を想定して査定を行います。
- STEP 3買主層を絞った販売活動 or 自社買取提案
- 一般ユーザー向けには難しい場合も、業者や投資家などニッチなニーズに対応できるルートで売却を進めます。当ショップによる直接買取も可能です。
注意したいポイント
- 建物を建てにくい=住宅需要が低い場合が多い
設計の制限や建築コストが割高になることから、一般の買主にとっては敬遠される傾向があります。 - 資産価値の見せ方が重要
形状が悪くても「小規模商業用地」や「近隣住民の買い増し地」など、用途を明確にすることで価値が伝わりやすくなります。 - 路地状敷地やセットバックの可能性に注意
不整形地では法規上の制限(接道義務・セットバック)が隠れていることも。早期の法令確認が不可欠です。
“売れにくそう”な土地も、適切な相手に届けば売れます

狭小地や不整形地は、万人向けではない代わりに、ぴったり合うニーズに届けば、むしろ即決につながることもあります。
当ショップでは、その土地の“使い道”を最大限に引き出す査定・提案・売却戦略をご提供しています。
「こんな形じゃ売れないのでは…」と思う前に、まずは私たちにご相談ください。
事故物件でも売却できます。告知義務と価格の現実、そして対策
事故物件とは?

事故物件とは、物件内または敷地内で死亡事故(自殺・殺人・孤独死など)が発生した過去がある不動産のことを指します。
こうした物件は「心理的瑕疵(かし)あり」とされ、売却時に買主へ告知する義務(告知義務)が発生する場合があります。
近年では、孤独死や高齢者の自然死を含むケースも多く、特に相続した物件で発生することが増えています。
「こんな家、売れないのでは…」と感じる方も多いのですが、実際には事故物件専門の買取ニーズや、一定の割安感を求める買主層も存在します。
事故物件を売却する時の流れと注意点
- STEP 1事実関係・経緯の確認
- 事故や死去の状況(種類・時期・場所)を整理し、告知義務の有無・範囲を確認します。
- STEP 2査定と販売戦略の決定
- 通常の相場と比較した上で、「事故の影響をどこまで価格に反映するか」「リフォームを行うか」などの判断を行います。
- STEP 3買主のターゲット選定・売却活動 or 買取対応
- 一般流通では売りづらい場合も、事故物件に理解のある投資家・専門業者向けのルートで売却。当ショップでの直接買取も対応可能です。
注意したいポイント
- 告知義務を曖昧にするとトラブルの原因に
内容をあいまいにしたり隠したりすると、後に損害賠償請求や契約解除などのトラブルに発展するおそれがあります。
当ショップでは、法的観点もふまえて誠実かつリスクの少ない伝え方をご提案します。 - 売却価格は通常より下がるのが一般的
心理的影響を考慮した価格設定が必要になりますが、「すぐ売りたい」「現金化したい」など条件次第では高値成立も可能です。 - 遺品整理・リフォームも併せて検討を
室内状況によっては残置物の処分や部分リフォームが有効な場合があります。弊社でワンストップ対応が可能です。
事故物件は“売れない”ではなく“売り方次第”
事故物件は「売れにくい」と思われがちですが、買主層のターゲティングや価格調整、伝え方次第で売却は十分に可能です。
当ショップでは、心理的瑕疵を含む不動産の取扱い経験も豊富で、査定・販売・買取・残置物処分までトータルサポートいたします。
判断が難しいケースでも、お気持ちに寄り添いながら進めてまいりますので、どうぞ安心してご相談ください。
訳あり物件の売却を成功させるために知って
おきたい5つのポイント

訳あり物件(借地権・底地・再建築不可・狭小地・事故物件など)でも、ポイントを押さえた売却戦略を立てれば、適正価格・短期間での成約が十分に可能です。
ここでは、当ショップの経験から導き出した「売却を成功させるための重要な5つのポイント」をご紹介します。
【1】現状を正確に把握し、隠さず開示すること
建物や土地の状態、権利関係、過去の履歴など、ネガティブな情報も含めて正確に把握することが第一歩です。
事故歴や再建築の可否、契約書の有無など、あいまいなまま売却を進めると後のトラブルの元になります。
【2】“誰に売るか”を想定した販売戦略を立てる
訳あり物件は、万人受けする商品ではありません。
だからこそ、「どんな層が価値を見出してくれるのか?」を逆算して販売戦略を組み立てる必要があります。
投資家・買取業者・借地人・近隣住民など、適切なターゲット設定がカギとなります。
【3】価格は「安くすればいい」ではなく、“理由ある設定”が大切
相場より安くすれば売れると思われがちですが、それだけでは不信感を生むことも。
建築不可の理由や心理的瑕疵の内容を説明し、「この条件なら納得できる」と思える価格設定が大切です。
そのためには、根拠のある査定資料や説明力も重要になります。
【4】権利関係や手続きの専門家と連携しておく
借地・底地・相続未登記・共有不動産などは、法的な専門知識が必須です。
当ショップでは、司法書士・行政書士・弁護士などの士業と連携し、スムーズな手続きを支援しています。
【5】“最終手段”としての買取プランを持っておく
もし一般市場での売却が難航しても、買取保証や自社買取による出口戦略を確保しておけば安心です。
当ショップでは、売却活動と並行して買取価格も提示し、お客様が納得できる方法を一緒に考えます。
【まとめ】訳あり物件でも、売却は「戦略次第」で成功します
「売れにくい」と言われがちな物件こそ、適切な知識と経験を持つパートナーに相談することが、成功の近道です。
LIXIL不動産ショップ TOKYO ESTATEでは、訳あり物件の査定・売却・解決実績が豊富にあります。
不安や迷いのある方も、まずは一度、お気軽にご相談ください。
売れにくい物件、どうすれば?訳あり不動産のよくあるご質問
- Q借地権でも売れますか?地主が協力してくれないかもしれません。
-
A
借地権も売却可能です。ただし、売却には地主の承諾が必要なケースが多いため、事前の交渉が重要です。当ショップでは、地主との交渉や承諾取得もサポートいたします。
- Q底地を持っていますが、借地人と連絡が取れません。それでも売れますか?
-
A
借地人との関係状況によりますが、調整や通知手続き、第三者への買取提案なども可能です。状況に応じて、売却方法をご提案いたします。
- Q再建築不可の物件ですが、需要はありますか?
-
A
はい、投資家や業者、収益目的の購入者に一定の需要があります。建物をリフォームして賃貸に出すなどの活用方法もあり、買取にも対応可能です。
- Q狭小地や変な形の土地でも、本当に売れますか?
-
A
売れます。形状が特殊な土地でも、用途に応じてニーズがあります。周辺環境や活用方法を踏まえて査定・ご提案いたしますので、ご安心ください。
- Q事故物件でも売却できますか?説明義務が心配です。
-
A
事故物件でも売却可能です。告知義務の範囲は状況によって異なりますので、適切な説明方法を一緒に考えながら進めてまいります。
- Q権利関係が複雑で手を付けられません。相談しても大丈夫ですか?
-
A
はい、大丈夫です。共有不動産や相続登記未了のケースも、士業と連携して対応しています。まずは現状をお聞かせください。
- Q他社で「うちでは扱えない」と言われました。それでも相談できますか?
-
A
もちろんです。当ショップは、他社で断られた物件の対応実績が多数あります。まずは一度、物件の状況をお知らせください。
- Q相談したら売却を急かされませんか?
-
A
ご安心ください。当ショップでは無理な営業は一切行っておりません。検討段階のご相談や、セカンドオピニオンとしてのご利用も歓迎しております。
上記にないお悩みも、お気軽にご相談ください
訳あり不動産の売却は、“どこに相談すればいいかわからない”こと自体が大きなハードルです。
当ショップでは、不安な気持ちに寄り添いながら、明確な解決策をご提案いたします。
“売れない”を、終わらせましょう。まずは無料相談から

訳あり物件の売却は、専門的な知識・柔軟な対応・調整力が求められます。
当ショップでは、借地権・底地・再建築不可・狭小地・事故物件など、他社が扱わない物件にも対応できる体制と実績があります。
「こんな物件、売れるのかな?」「何から始めたらいいかわからない」
そんな不安こそ、私たちにご相談ください。
地主との調整、残置物処分、手続き代行、買取保証までワンストップで対応可能です。
東京都北区を中心に、豊島区・板橋区・練馬区・文京区まで幅広く対応しております。
まずは無料査定・無料相談から、お気軽にご連絡ください。