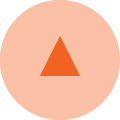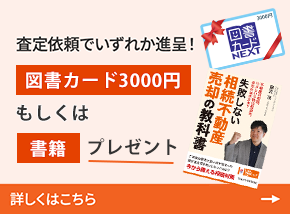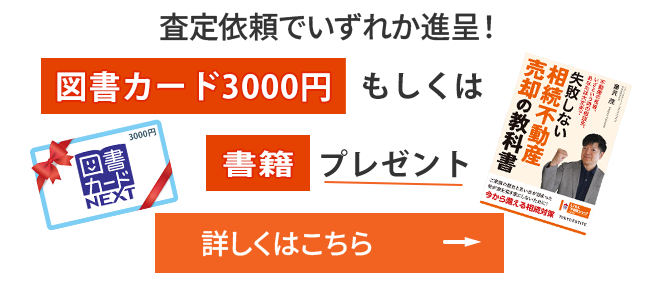Inheritance
相続した不動産を売却したい方へ
- ホーム
- 相続した不動産を売却したい方へ
目次
親から相続した土地・戸建て、どうする?
登記・売却・活用まで徹底解説
親から土地や一戸建てを相続したものの、「どうすればいいのかわからない」「放置してしまっている」という方も多いのではないでしょうか。
相続不動産の扱いには、名義変更(相続登記)や税金の特例など、期限のある重要な手続きが数多くあります。
このページでは、相続登記義務化のポイント、相続後3年以内の売却メリット、売却・活用方法、進め方のステップまで、わかりやすくご案内します。
LIXIL不動産ショップ TOKYO ESTATEでは、東京都北区を中心に、豊島区・板橋区・練馬区・文京区の相続不動産に対応実績が豊富です。
相続不動産の“わからない”をそのままにしない。
当ショップの4つの強み
相続登記から売却まで、全ての手続きをワンストップで対応

「何をすればいいかわからない」「名義変更がまだ…」という方もご安心ください。
当ショップでは、司法書士・税理士と連携し、相続登記、税金相談、売却手続きまで一括サポート。
手続きが複雑な土地・古家・空き家の相続でも、最初の一歩からしっかりサポートいたします。
東京都北区・豊島区・板橋区・練馬区・文京区の相続不動産に精通

相続不動産は立地や用途地域、接道条件などによって価値が大きく変わります。
当ショップは東京都北区を中心とした地域に密着し、多数の相続不動産の査定・売却実績あり。
不整形地や再建築不可などの“難あり物件”にも対応可能です。
「売るか貸すか迷っている」方への収支比較提案

相続した土地や家をどう活用するか迷われている方には、売却価格と賃貸収入のシミュレーションを両方ご提示。
賃貸併用住宅や駐車場活用など、収益を得ながら資産を残す方法もご提案可能です。
「すぐに売らずに検討したい」という方もお気軽にご相談ください。
遠方在住・多忙な方も安心のオンライン&夜間対応

相続人が遠方にお住まいのケースや、平日の日中に動けない方もご安心ください。
Zoom・LINEでのオンライン相談、夜22時までの予約対応も実施しています。
現地確認や売却活動も、来店不要で進められます。
相続した不動産をそのままにしておくと、税金・老朽化・登記義務違反など、将来のトラブルに繋がる可能性があります。
LIXIL不動産ショップ TOKYO ESTATEでは、法務・税務・活用までトータルで対応できる体制を整えています。
「何から始めればいいのか分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。
Pick
UP!放置はNG!2024年4月から義務化された「相続登記」とは?

相続登記とは、不動産を相続した際に、法務局で名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。
これまでは任意でしたが、2024年4月からは義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
「使っていない」「売る予定がない」物件でも対象となり、正当な理由なく放置した場合、最大10万円の過料(罰金)が科される可能性も。
相続した不動産は、まず登記手続きを済ませておくことが、後々の売却や活用への第一歩です。
もし相続登記がまだの方もご安心ください。当ショップでは、司法書士と連携し、初めての方にもわかりやすく丁寧にサポートいたします。
“もったいない”ことになる前に。相続した不動産の売却を「3年以内」におすすめする理由

不動産を相続したあと、「とりあえずそのままにしておこう」と放置してしまう方も少なくありません。
しかし、相続した不動産の売却には“3年以内”に売ることで使える節税制度があるのをご存じでしょうか?
それが「取得費加算の特例」です。
これは、相続税を支払った場合に、支払った相続税の一部を不動産の取得費(購入費用)に加算して、譲渡所得税を軽減できる制度です。
つまり、3年以内に売却すれば、売却益(譲渡所得)を減らすことができ、結果的に支払う税金を少なくできる可能性があるのです。
制度を利用できるかどうかで、数十万円〜数百万円単位の差が出ることもあります。
取得費加算の特例の注意点
この「取得費加算の特例」にはいくつかの条件があり、すべてのケースで使えるわけではありません。
- 相続税を納めていること(相続税の課税対象になった場合)
- 相続開始を知った日の翌日から3年以内に売却すること
- 売却した不動産が相続財産に含まれていたこと
- 一定の親族間売買でないこと(不当な節税とみなされないため)
また、3年ギリギリで動き出しても、買主が見つからなければ期限を超えてしまうこともあるため、「使わない不動産を相続した場合は、早めに動き出す」ことが非常に重要です。
相続した不動産は、放置するほど税制メリットを受けにくくなり、維持費やトラブルのリスクも高まります。
「今すぐ売るか決まっていない」という方でも、まずは状況を整理し、3年以内の売却を選択肢に入れて検討してみましょう。
当ショップでは、税理士との連携により、特例の可否や節税シミュレーションにも対応しています。節税を最大限活かすためにも、ぜひお早めにご相談ください。
使わない実家・土地、どうする?
売却・活用方法と対応サービスのご案内

相続した一戸建てや土地は、「とりあえず保有しているけれど、どうしたらいいかわからない」という方が非常に多くいらっしゃいます。
当ショップでは、そうした方のために、「売る」「貸す」「残す」という3つの選択肢に対し、それぞれのメリット・注意点をご説明した上で、お客様にとって最適な方法をご提案します。
「売却したい」なら
- 仲介による売却活動(広告掲載・内見対応・交渉代行)
- 当ショップによる直接買取のご提案(スピード重視の方向け)
- 古家付き土地・再建築不可物件など売却困難な不動産にも対応
▶ こんな方におすすめ
「現金化して整理したい」「遠方に住んでいて管理が難しい」「共有名義で早く分けたい」
「貸したい・活用したい」なら
- 空き家の部分リフォーム+賃貸活用提案
- 更地にして月極駐車場や資材置き場への転用
- 古家を残したまま倉庫・作業所としての短期賃貸など
▶ こんな方におすすめ
「売るにはまだ迷いがある」「定期収入を得ながら様子を見たい」「相続人で話し合いながら使いたい」
「残したい・維持したい」なら
- 空き家の見回り・清掃・草刈りなどの管理サポート
- 将来的な売却を見据えた不動産の価値査定と保全提案
- 名義整理・相続人間の共有調整なども対応
▶ こんな方におすすめ
「とりあえず手放したくはない」「親族で相談中」「将来的に住む可能性もある」
当ショップなら相続した不動産の売却・活用を全面サポート!
対応サービス
- 売却・活用の判断材料としての査定・活用案の提示(無料)
- 司法書士・税理士と連携した、相続登記・税務対策の提案
- 解体・残置物処分・測量・境界確認・近隣対応なども一括サポート
相続した不動産には「売る」以外にも選択肢がありますが、判断を先延ばしにすることで税制の特例を逃したり、維持費がかさんでしまうケースが多く見られます。
まずは、売却・賃貸・保有、それぞれの可能性を比較してみるところから始めてみませんか?
LIXIL不動産ショップ TOKYO ESTATEでは、地域の特性や物件の状態をふまえた、実現可能な活用プランをご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
相続した不動産の相続発生から売却までの流れ
相続した土地や戸建てを売却・活用するためには、いくつかの重要なステップと期限が存在します。
ここでは、相続が発生してから不動産を売却できる状態になるまでの流れを、必要な手続きと期日、書類情報と合わせてご案内します。
- STEP 1遺言の有無を確認する【目安:相続発生直後~1週間以内】
-
必要な手続き遺言書の確認・検認手続き(必要に応じて)
被相続人の遺言書がある場合、相続内容や不動産の承継者が明記されていることがあります。
特に自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。- 必要書類:遺言書、戸籍謄本(被相続人)など
- 入手・提出先:戸籍謄本は市区町村役場、遺言書の検認は家庭裁判所へ
※公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要です。
- STEP 2相続人を確定する【目安:1週間~1か月以内】
-
必要な手続き戸籍の収集・相続関係図の作成
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。
想定外の相続人が見つかる場合もあるため、早めの確認が重要です。- 必要書類:被相続人の戸籍謄本一式、相続人全員の住民票・戸籍
- 入手先:本籍地の市区町村役場
- STEP 3相続財産の把握・財産目録の作成【目安:1~2か月以内】
-
必要な手続き財産目録の作成(任意)
相続対象となる資産・負債を一覧化し、相続人間で内容を共有します。
土地や家屋、預貯金、株式、借入金などをもれなく整理する必要があります。- 必要書類:不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど
- 入手先:登記簿謄本は法務局、評価証明書は市区町村役場
※不明点が多い場合は税理士に相談するのも安心です。
- STEP 4遺産分割協議をおこなう【目安:~3か月以内に開始】
-
必要な手続き遺産分割協議書の作成誰がどの不動産を相続するかなどを相続人全員で話し合い、合意内容を文書にまとめます。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所への調停申し立ても可能です。
- 必要書類:相続人全員の印鑑証明書、署名・押印のある遺産分割協議書
- 入手先:印鑑証明書は各相続人の住民登録のある市区町村役場
- 提出先:遺産分割協議書は相続登記や金融機関の手続きに使用します
- STEP 5相続登記を法務局に申請する【目安:3年以内に必ず実施】
-
必要な手続き相続登記(義務化対象)
2024年4月より、相続で不動産を取得した場合は相続登記が法律上の義務になりました。
手続きを怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がありますので注意が必要です。- 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
- 相続人の住民票、印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 提出先:不動産の所在地を管轄する法務局
- 必要書類:
- STEP 6相続税の申告・納付(必要な方のみ)【目安:10か月以内】
-
必要な手続き相続税の申告・納付相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税が発生します。
期限を超えると延滞税や加算税が発生するため注意が必要です。
- 必要書類:財産目録、評価書、申告書、戸籍謄本など
- 提出先:被相続人の住所地を管轄する税務署
相続不動産の売却・活用でよくあるご質問
- Q相続登記がまだですが、売却はできますか?
-
A
売却するには、まず相続登記によって不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
当ショップでは、提携司法書士と連携し、相続登記の手続きから売却完了までをワンストップで対応しております。
登記がまだの方も、まずはご相談ください。
- Q相続した土地や家を売るか貸すか迷っています。両方相談できますか?
-
A
はい、どちらもご相談いただけます。
当ショップでは、売却価格と賃貸収入のシミュレーションを比較し、収益性や維持コストをふまえた最適な方法をご提案します。
迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。
- Q再建築不可や古家付きの土地でも売却できますか?
-
A
はい、可能です。
当ショップでは、再建築不可・狭小地・旗竿地・老朽建物付き土地などの“訳あり不動産”にも対応実績があります。
物件の特性を活かした販売戦略や買取のご提案も可能です。
- Q相続人が複数いますが、売却は可能ですか?
-
A
相続人全員の同意があれば売却可能です。
共有名義や相続分が分かれているケースでも、遺産分割協議や名義整理からご相談に応じます。
話し合いが難しい場合には、調停人資格を持つスタッフがご支援することも可能です。
- Q親の家を相続したけれど、遠方で動けません。対応できますか?
-
A
はい、ご安心ください。
当ショップでは、オンライン相談(Zoom・LINE)や郵送対応が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- Q相続税の対象になるか、事前に確認することはできますか?
-
A
はい、可能です。
相続税が発生するかどうかの判定は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)をもとに判断します。
当ショップでは税理士との連携により、簡易的な試算や節税のご相談も承っております。
- Q売却する予定はまだないのですが、相談だけでも大丈夫ですか?
-
A
もちろん大丈夫です。
「将来的にどうしようか考えている」「今すぐではないけれど登記や相続手続きに不安がある」という段階から、無料でご相談を承っております。
相続不動産の売却・活用は、ご家庭ごとに状況もご希望も異なります。
どんな些細なことでも、LIXIL不動産ショップ TOKYO ESTATEが丁寧にお話を伺い、最適な進め方をご提案いたします。
相続した不動産の“そのまま”を、今こそ見直してみませんか?

「名義変更がまだ」「売るべきか貸すべきか迷っている」「遠方で動けない」──
相続した土地や家をどうするかは、人生でも大きな判断のひとつです。とはいえ、すべてを一人で抱える必要はありません。
当ショップでは、相続登記・売却・賃貸・活用・税金対策までをワンストップでサポートいたします。
司法書士・税理士との連携体制もあり、初めて相続を経験される方も安心してご相談いただけます。
東京都北区を中心に、豊島区・板橋区・練馬区・文京区で多数の相続不動産対応実績があり、オンライン相談・夜22時までの事前予約対応も可能です。
「とりあえず相談だけしてみたい」という段階からも歓迎します。まずは無料相談・無料査定から、お気軽にご連絡ください。